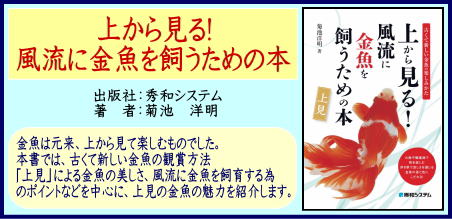
金魚カタログ |
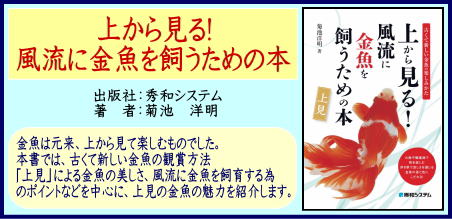
金魚カタログ |
| 朱文金(シュブンキン) | |
 |
|
| ●品種名 | 朱文金(朱分錦) |
| ●読み方 | シュブンキン |
| ●出現年代 | 明治25年〜 |
| ●作出国 | 日本 |
| ●作出者 | 初代秋山吉五郎氏 |
| ●歴史・過程 | 明治25年、初代秋山吉五郎氏が三色出目金とヒブナ及びフナ尾の和金との交配によって、作出。 明治33年に農商務省水産講習所の松原新之助氏により「朱文金」と命名され、明治35年に発表された。 本来は「朱文錦」と書き、朱(赤)の色合いと浅葱色(青)を基調とした鮮やかな体色を持つ錦のような金魚という意味で名付けられた。 |
| ●特徴 | 和金型の体型に長いフキナガシ尾、体色が赤、青、白、黒の和を感じさせる渋い雑色、モザイク透明鱗が特徴の味わい深い品種。 体色以外の体型はコメットと同様。作出にフナが使われたこともあり、非常に丈夫で長生きする。 |
| ●入手難易度 | 【容易】 日本人にはお馴染みの品種で、入手も容易。一般の金魚屋さん、ホームセンターで売られている。 |
| ●飼育難易度 | 【容易】 丈夫で、長生きし、大きな飼育槽で飼えば30cm以上に大型化する。 |
| ●画像の個体 | (上):2013年日本観賞魚フェアに出展されていた個体。 (下):2006年静岡県金魚品評大会、朱文金親魚の部で最優秀賞を獲得した個体。本来は横から観賞すること(横見)が多い。 |
| ●その他 | 派生品種に、日本の朱文金をもとにイギリスで改良された、ハート型の尾を持つ「ブリストル朱文金」がある。 イギリスの熱心な愛好家により飼育され、イギリス国内から長く持ち出されていなかったが、近年、少数ではあるが日本にも輸入されはじめた。 |
| 和金型の金魚 | 琉金型の金魚 | オランダ型の金魚 | らんちゅう型の金魚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
金魚カタログメニューに戻る |
 |
 |