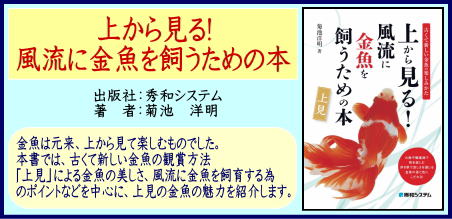
金魚カタログ |
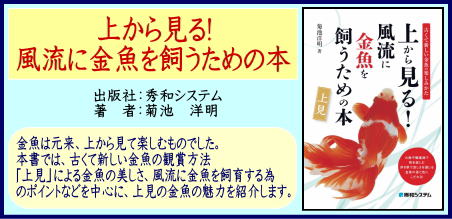
金魚カタログ |
| 蘭鋳(らんちゅう) | |
  |
|
| ●品種名 | 蘭鋳 |
| ●読み方 | ランチュウ |
| ●出現年代 | 幕末、明治初期〜 |
| ●作出国 | 日本 |
| ●作出者 | 初代石川亀吉 |
| ●歴史・過程 | 1748年に発行された現在確認されている日本最古の金魚飼育書・安達喜之著「金魚養玩草」(きんぎょそだてぐさ)にすでに「卵虫」として記されていることが確認されている。 しかし、当時のランチュウは、現在のような肉瘤の発達したランチュウではなく、「マルコ」と呼ばれるランチュウの原始となる肉瘤の発達していない金魚だった(マルコ自体は江戸時代、オランダ人により中国から長崎の出島に持ち込まれたと言う)。 現在の肉瘤の発達したいわゆる獅子頭ランチュウは、幕末、明治にかけて、東京の初代石川亀吉氏らが家業を投げ打って改良に取り組み、現代ランチュウの基礎を築いた。以後、愛好家・養魚家らによりさらに改良が重ねられ現在に至る。 |
| ●特徴 | 体型は丸くて短く、背ビレがない。尾ビレは太くて短い尾筒に対して、角度をつけて伸びている。頭部の肉瘤は豊かに発達するが、バランスよく発達した魚が良いとされている。柄は赤のみ、赤と白(更紗)、白のみが原則で、黒が入らない。 ランチュウのように背ビレのない金魚は、上から観賞することが基本とされている。 |
| ●入手難易度 | 【普通】 高級金魚の代名詞ではあるが、入手するのは難しくない。ただ、優良魚は他の品種より一、二桁多い金額で売られている。 |
| ●飼育難易度 | 【普通〜難しい】 観賞用として飼育する分には特に難しさはない。ただし、品評会で勝てるような魚を作るのは、病気や短命など様々な難しさがある(らしい)。 |
| ●画像の個体 | (上):2013年日本観賞魚フェアに出展され入賞した秀逸な個体。 (下):画像の個体は、初代石川亀吉氏から脈々と続く東京の石川養魚場の品のある当歳魚。 優良魚になる素質を充分に備えた固体。石川養魚場レポートはコチラ! |
| ●その他 | 「蘭鋳」という漢字は、正確には「魚」+「蘭」、「魚」+「寿」と書く。(常用外) |
| 和金型の金魚 | 琉金型の金魚 | オランダ型の金魚 | らんちゅう型の金魚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
金魚カタログメニューに戻る |
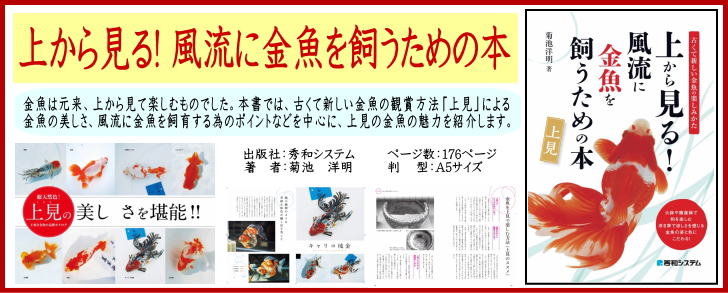 |
 |